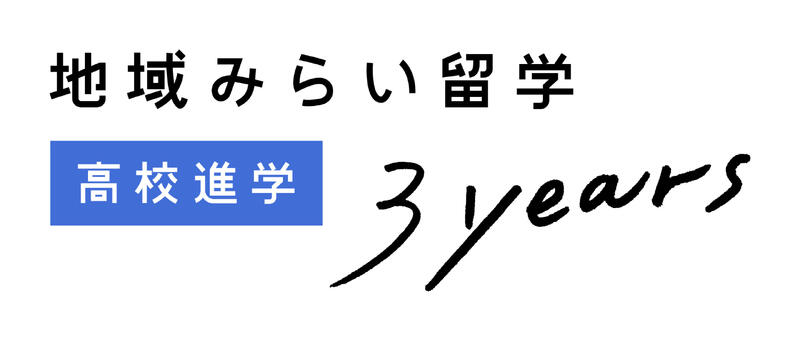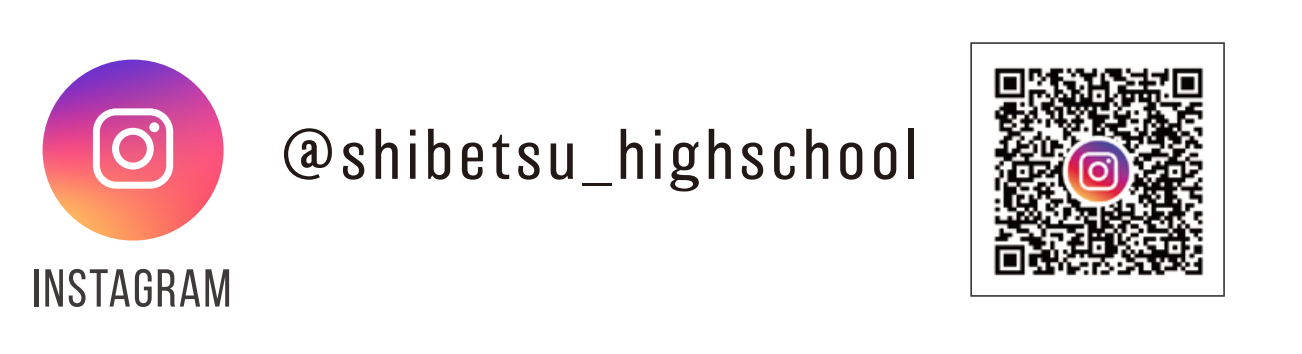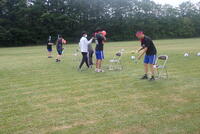ー こちらからも確認いただけます! ー
【年間行事予定(2025年)】→ 25 年間行事予定 (生徒配布用).pdf
【シラバス】 1学年 → 1学年.pdf
2学年 → 2学年.pdf
3学年 → 3学年.pdf
・標津高校学校紹介movie
・令和7年度より全国募集を開始します。
・標津高校Instagram始めました。
・令和7年度版学校案内パンフレット
標高ニュース
自然環境系科目 苗の定植
7月1日(火)夏らしく日差しも気温も上昇中。本日の探究基礎は、畑作りです。前日に3年生が畝を立ててくれたところにマルチシートを貼り、いよいよ苗を植えることとなりました。
種から育てたカボチャにズッキーニ、トウモロコシの苗をきれいに定植しました。今年は、暑さも続き順調に育っています。また、苗から育てているトマトにキュウリも定植しました。キュウリは、すでに小さな実が実っていました。まだ植えていない苗もまだあります。これからしばらく定植作業が進みます。
標津水産教育プログラム 高大連携 水産出前講座
6月30日(月)2年生の総合的な探究の時間、前回のクロガレイの捌き方体験の続きである高大連携企画の水産出前授業が行われました。今回の講師は、東京農業大学オホーツクキャンパス水圏生産科学研究室准教授の市川先生です。
「水産から地域を学ぶ~産業と人のあり方を探る~」というテーマで講話をいただきました。標津町の漁業は、実は、日本海側のある県一県分の漁獲量があることや日本の食糧自給率、魚種によるレジームシフトが起こることで漁獲される魚が変化することなど学びました。さらに、サケやニシンという標津になじみある魚について、漁業という視点で詳しく解説していただきました。
地域の産業について考えることが地域の未来を考えることに繋がっています。そして、日本の未来に繋がっています。市川先生、お忙しい中お越しいただき、ありがとうございました。
地域循環型防災教育 川北小学校4年生来校
6月30日(月)、先日、川北小学校4年生で防災の出前授業を行ったところですが、本日は、その4年生が来校してくれました。地域の防災施設の見学ということで、町役場住民生活課危機管理室と共同した防災学習の一環です。
学校に来てもらった理由は・・・標津高校が避難所だからです。
学校にある避難所設備を見てもらいました。まずは、非常用の大きな発電機。発電機があると、停電でも様々なことに対応することができます。子供たちもスマホの充電ができる!とか暖房使える!など考えを発表してくれました。その次は、体育館と格技場での防災で使えるもの探検。ホワイトボードは「頭を守るのに使えそう」とか「卓球台は机にできる」とか子供たちは想像力を発揮していました。
防災用の卓球の仕切りを紹介すると、早速寝袋に・・・いざというときにマットにもなるし、寝袋にもなる。日常学校にあるもので十分災害に対応できるということがわかってもらえたでしょうか。
地域循環型防災教育がまたひとつつながりました。
スポーツ大会
4年ぶりに外でのスポーツ大会!
縦割りでのチームを編成し、ピンク、黄色、水色のはちまきで出場です。
まずは選手宣誓。各チームのリーダーがユーモアのある選手宣誓で幕を開きました。
外に移動して、玉入れ、綱引き、綱とり、大縄跳び。
どの競技も白熱した接戦の展開で応援にも熱が入ります。
午後からはアンケートで人気の高いリレー、障害物競走。
障害物競走は笑いに溢れ、リレーは生徒全員が力走を見せました。
優勝した黄色チームはメダルを下げて記念撮影。
どの種目も盛り上がり充実した一日となりました。
ノリウツギ学習 和紙漉き体験
6月26日(木)ノリウツギ学習を行いました。2年生の自然環境系科目選択生徒3名で、標津町文化会館で行われた紙すき体験に参加しました。標津町で採集されるノリウツギは、大切な和紙作りの要素「ねり」となります。今回は、和紙に触れ、ノリウツギを知ることを目的としました。
テレビとかでは、見たことのある和紙作りですが、実際漉く作業をやってみるとこれが難しい。均等に繊維を乗せているつもりでも講師の先生がちょっと修正してくれます。とても繊細で職人の仕事ということを感じます。漉いた和紙に思い思いに色をつけ、乾燥させて完成です。
この後、標津町内のノリウツギをテーマに学びを深めていきます。
畑作業~地産地消を学ぶ~
3年生のフードデザインの授業では、地産地消を体験的に学ぶため理科と教科横断で畑実習を行っています。
今年もその季節がやってきました!
各自長靴を用意して、日焼け対策をして、準備万端です!
第一弾は、じゃがいもを植えるための畝立てを行いました。
理科の先生からレクチャーを受けてスタート!
第二弾は、草むしりです。炎天下の中、2時間かけて丁寧に草むしりを行いました。
第三弾は、芽かきと土寄せと追肥の作業です。
地道な作業こそ、丁寧さが求められます。汗だくでみんな作業を頑張りました!
目標はじゃがいも収穫100kg!引き続き、頑張りましょう!
今年も町民農園を貸していただき、地域関係者の皆様に感謝申し上げます。
標津高校PR大使 川北中学校編
6月25日(水)川北中学校にて、標津高校のPRをさせていただきました。貴重なお時間ありがとうございます。
生徒会生徒8名で学校PRスライドで学校の説明をして、標津高校の魅力を伝えました。また、今年のPR動画も披露。小さい学校だけどとても仲が良くみんながいきいきしている様子が伝わったでしょうか。後半は、生徒インタビュー。標津高校の魅力を生徒会メンバーから伝えてもらいました。学年を超えて仲が良いことや行事が楽しいこと、防災の学びで自分が成長できたこと、資格検定に頑張れることなどなど。
7月は、学校祭、9月は体験入学と高校を体験する機会があります。是非、中学生の皆さんご来校ください。
地域循環型防災教育 川北小学校へ
6月25日(水)地域循環型防災教育の一環として、町内川北地区の川北小学校4年生に対して、防災出前授業を行いました。生徒会8名がそれぞれのパートに分かれ、子供たちに伝わるように工夫して授業に取り組みました。
今回の内容は、昨年度に取り組んだ防災研修の報告と絵本の読み聞かせ。熊本・長崎で学んだ地震や水害、火山災害を元に子供たちに伝わるように工夫したパワポをつくり、また、授業の後、気象台の津波発生装置による学習もあったので、福島の請戸小学校物語を読み聞かせしました、絵本に出てくる「あなたにとっての大平山」、標津町だったらどこになるのか想像してもらえたでしょうか。災害にとても大切なキーワード「備える」を家に帰ってから、おうちに人と共有してくれたらありがたいです。
海洋教育 藻場学習
6月24日(火)海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で取り組む藻場学習を行いました。大潮の干潮時を見計らい3,4時間目に実施。本日の講師は、昨年度からご協力いただいている標津サーモン科学館副館長の西尾さんです。
標津町には,海辺で遊び、キャンプもできる素敵な公園が整備されています。町民の憩いの場所です。ここに造成されている人工の海岸で藻場を造っています。先月、海洋学習の第1弾として春のプランクトン観察をしました。そのときにたくさんの動物・植物プランクトンを観察しました。これらの生き物の繋がりを藻場学習で深める単元です。
まずは、とにかく生き物をたくさんの種類見つけることです。真っ先に捕まえたのがカニ類でした。そして、西尾さんの指導で稚魚を探してみました。すばしっこいウグイの稚魚や生まれたてのカジカ、ギンポの仲間を観察することができました。その後は、ヤドカリ、巻き貝、カサガイ、ゴカイ、ヘラムシ、フジツボ、海藻を観察。小さな藻場でしたが、多様な生物が生息し、互いに関係を作り、豊かな海が醸成されていました。
本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で行われました。
避難訓練(火災)
6月16日(月)の6時間目に避難訓練を実施しました。
授業中に調理室で発生した火災に対し、駐車場への避難という想定で行いました。
放送による避難指示から、避難後の人数確認完了までの時間を計測します。今年は1分51秒でした。
生徒も教職員も緊張感を持ちつつ、冷静に避難することができました。
標津消防署職員の方から、教職員は生徒に適切な避難指示が出せること、生徒は先生の避難指示をしっかり聞くことが一番大切だというお話をしていただきました。
また、校長先生から、実際に起きた学校での火災を例に、いつ起こってもおかしくない身近な災害であり、起こった際には命を守る行動を最優先にとってほしいというお話をしていただきました。
その後、各クラスの代表者に避難梯子を使用した避難の実演をしてもらいました。
地上で見ていた生徒から「がんばれ~!」という声をかけられながら無事に避難することができました。
今回も生徒だけでなく教職員にとっても防災減災意識が高まる避難訓練となりました。
ご協力いただいた標津消防署職員の方々、ありがとうございました。
所在地
〒086-1652
標津郡標津町
南2条西5丁目2番2号
TEL
0153-82-2015(事務室)
0153-82-2364(職員室)
FAX
0153-82-2021
年間行事予定表