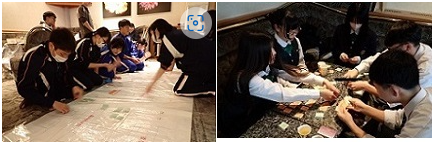標高ニュース
令和5年度 強歩遠足
9月29日(金)に令和5年度強歩遠足が行われました。バスでスタート地点である第二しべつ展望パーキングへ移動し、元気よく笑顔でスタートしました!
ゴールまでは約8.5kmの道のりです。
途中のチェックポイントで給水休憩をし、スタンプカードにスタンプを押して、校長先生が先導し、全校生徒でゴールの標津高校を目指します。
校長先生を抜かしてはいけないというルールを皆守り、ゴミを拾いながらも、景色を楽しむ人、ゴールを目指し黙々と歩き続ける人、友人と他愛もない会話をしながら歩く人、皆それぞれの楽しみ方で歩いていました。
ゴール後にはPTAのお母さん特製の豚汁が待ってます。疲れ切った後に食べる豚汁は最高です!
今回の強歩遠足を無事に実施できたのは、保護者様、多くの地域の関係者のご協力のお陰です。この場を借りて、御礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。
海洋教育 サケ学習(人工授精)
10月5日(木)標津サーモン科学館にて「サケ学習」に取り組みました。鮭の聖地の物語が始まる標津町ならではの学習です。
今回は、自然環境系2年生でサケの人工授精と解剖実習、生理学から経済学まで幅広い学びが展開されました。本日の講師は、学芸員の仁科さん。お互い緊張しながら実習が始まりました。
サケの説明をする仁科学芸員
まずは、サケの送り方。送る=絞める、サケを神の国に送る方法を学びました。送るときは、苦しませず、一気に、サケからの恵みに感謝して。
次は、採卵です。特殊なナイフ(採卵刀)を用いて、開腹し、オレンジ色の卵を取り出します。
採卵後は、人工受精です。水分が受精率を下げる要因ともなるので、水分に気をつけて、そして丁寧に精子と卵を混ぜ合わせます。そして、いよいよ受精の段階。混ぜ合わせた卵を水槽にそっと入れ、精子の動きを促します。うまく受精できたかな。
丁寧に扱います。 そっと水に入れて受精完了
受精後は、しばらく安静にします。その間に卵の変化を確かめたり、魚類の進化、感覚器官、内臓の観察を行いました。受精卵は、はじめは柔らかく落としても弾みませんが、1時間後に同じ事をしてみると・・・弾みました。卵の膜が硬化したようです。
あっという間の2時間の実習。鮭の聖地の物語はたくさんの学びをもたらしてくれました。受精卵は、11月~12月に本校へ移し、発眼卵の管理から孵化、稚魚の飼育に続きます。
この授業は、標津サーモン科学館の協力と海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行われています。
第72期生徒会役員認証式
10月4日、後期始業式の後、生徒会役員認証式が行われました。最初、校長先生から激励の言葉を頂き、認証状を受け取りました。
その後、生徒会長から、72期は「切磋琢磨」をテーマに活動することが発表されました。以下、会長の言葉を要約したものです。
「私達が72期で大切にしたいことは、他学年交流と、仲間意識をもつことです。
これまでの学校行事では、学年間の壁を感じる場面が多くありました。
生徒人数が少ないからこそできる全学年の交流を増やし、標津高校の魅力にしていきたいです。また、今までの行事でどこか他人事にも思える様子もみられていたので、仲間意識を大切にしてこれから活動していきたいと思いました。前年度でも他学年交流を目標にしていたこともあり、新しくイベントを企画することもできました。これを継続し更に良いものにしていきたいです。お互いに声をかけあい、励まし合いながら、学年だけでなく標津高校全体をよくしていけるよう、私達生徒会と一緒に活動してくれると嬉しいです。」
72期生徒会の皆さんの活躍を期待しています!
給食メニュー開発試食会(3年フードデザイン)
10月5日(木)フードデザインの授業にて、給食メニュー開発試食会を行いました。
標津町給食センターのご協力のもと、12月11日(月)から5日間、標津高校のフードデザインの授業にて生徒が考案したメニューで給食を提供させてもらいます。
標津小学校・中学校の皆さんのアンケート等を参考にしながら、標津町の皆に喜んでもらえる給食メニュー作りを半年間行ってきました。
今回の試食会を開催するため、前日には、標津町役場の水産課の職員の方に講師として来て頂き、ニシンの下ごしらえの仕方を教えてもらいました。
5つのグループごとに、標津町の特産品を使用したメニューを考え、作りました。
ニシンやホタテや鮭、標津ゴーダチーズや標津牛乳、標津羊羹も使用しています。
調理室の様子を見に来てくれた先生方にも試食をしてもらいました。
本日の試食会のゲストは、標津町教育長さん、標津町教育委員会の課長さん、本校の校長先生です。
生徒は緊張と不安の中でしたが、グループごとにそれぞれのメニューへの思いや、特徴を説明し、試食をしてもらい、貴重な感想を頂きました。
今回の試食会で頂いた貴重なご意見をもとに改良していき、12月の給食メニュー実現まで頑張っていきたいと思います。
前期終業式
9月29日(金)の6時間目に前期終業式を行いました。
まず、全道大会で入賞した陸上競技部と、夏季休業期間中に行っていたサプリコンクールの入賞者の賞状伝達を行いました。
次に、校長先生から強歩遠足の講評をいただきました。また、人生はマラソンのようなもので、大変なことを乗り越えた先に大きな喜びが待っているというお話をしていただきました。
強歩遠足後ということで生徒は疲れ切っているかと思いきや、歩く距離の短縮とPTAの方々が作ってくださった豚汁のおかげで、皆元気そうな様子で前期を締めくくることができました。後期も生徒の活躍に期待したいと思います。
生徒会リーダー研修(2日目)
10月2日、朝6時30分・・・生徒会役員の朝は早い。頭をリフレッシュさせるため早朝散歩へ。阿寒湖畔を散策し、朝食を済ませ、2日目の話し合いへ。
午前は、HUG以外の防災ゲームの紹介や、生徒会とボランティア部が協働で全校生徒に声をかけ、可能なボランティア活動を行うこと、最後に新生徒会役員は個人目標を宣言して2日間の日程を終わりました。
(↓お世話になったホテル前で)
この2日間で話し合われたことを活かし、今後の学校行事運営を頑張ってほしいと思います。
後期始業式で72期の目標が発表されます。
生徒会リーダー研修(1日目)
10月1日(日)、2日(月) 生徒会リーダー研修を行いました。
例年この時期に新旧生徒会の引継ぎ、新生徒会の目標設定、学校の課題等を集中して
話し合うために学校を離れて実施しております。
今年も、阿寒湖の阿寒湖荘にお世話になりました。支配人・社長がお出迎えしてくれました。(毎年会議室の準備等快適な話し合いの空間を提供していただき、ありがとうございます)
早速話し合いスタート・・・と行きたいところですが、改めてお互いを知るということでアイスブレークを兼ねた「他己紹介」を行ってから、本格的な話し合いに入りました。
旧生徒会からの引継事項を受け、新生徒会の目標設定、活動計画を検討していきます。まだ若干緊張している役員もいるようですが、先輩役員がスムーズに話し合いをリードしてくれています。
後半は、防災に関する研修を行い、HUGの手順再確認やアップグレードに向けた作業を行いました。
1日目の話し合いもあっという間に終わり、残りは翌日に持ち越しとなりました。
(おまけ)1日目夕食・・・豪華でした!
体験入学 ようこそ標津高校へ
9月15日(金)令和5年度の中学生対象、体験入学が行われました。
近隣中学校から40名を超える生徒が体験に来てくれました。ありがとう!
今年度の体験入学は、体験重視。ということで、今年は、遠隔配信授業を札幌からお願いして配信授業の雰囲気を体験してもらいました。また、本校で取り組んでいるスタサプにも取り組んでもらいました。タブレットで操作しながら、自分の興味ある単元を体験。楽しそうに取り組んでくれました。
授業は、商業科の説明と自然環境系の授業の様子を紹介。先生方の熱いプレゼンが光りました。
遠くから時間を作ってわざわざお越しいただきありがとうございます。高校選択に是非、標津高校を入れてもらえると光栄です。
地域循環型防災教育 標津中学校出前授業
9月28日(木)標津中学校で出前授業を行いました。地域循環型防災教育の一環でもあるこの出前授業、今年は、生徒会の防災研修の報告とオリジナルHUGを行いました。
まずは7月に生徒会の生徒で行った防災研修のお話です。中学生に向けて、防災研修で学んだ事をわかりやすくスライドにまとめ発表しました。今年は、宮古市から釜石市、宮城県、そして、厚真町へ研修へ行きました。それぞれの地域で学んだり体験した事を伝える事ができました。途中のクイズを入れたり、中学生に答えを求めたり、和気藹々とした時間を過ごすことができました。
さらに、今年度は「とっさのひとこと」をやりました。こんな時なんて言うか?中学生でグループワークしてもらいました。どのグループもしっかりとした発表をしてくれました。
後半は、HUGです。毎年中学2年生とHUGを行っています。そして、今年は,新旧の生徒会役員でHUGの進行の仕方を引き継ぐ目的で、新旧の役員が混ざったチームで進行しました。中学生も活発に意見を言ってくれたり、みんなで一緒に考えたり、あっという間の50分間となりました。
シュガーセミナー(3年フードデザイン)
9月27日(水)、3年生フードデザインの授業にてシュガーセミナーを実施しました。
講師として、三笠市地域おこし協力隊の田中颯太様、市川竜之介様にお越し頂きました。
シフォンケーキ作りのデモンストレーションを見たあとに、各グループごとにシフォンケーキ作りをしました。
卵黄と卵白に分ける工程で苦労しましたが、講師の先生方にアドバイスをもらいながら取り組みました。
その後、砂糖に関する講義を聞き、砂糖と人工甘味料の味比べや、砂糖と人工甘味料で作ったクッキーの食べ比べを行いました。
また、大きなてん菜を持ってきてくれていたので、てん菜を間近で見ることもできました。
焼き上がったシフォンケーキはどのグループも大成功でした!!
このような貴重な体験をさせて頂き、心より感謝申し上げます。
道新サービスセンターの堀部様、三笠市地域おこし協力隊の田中様、市川様、どうもありがとうございました。
所在地
〒086-1652
標津郡標津町
南2条西5丁目2番2号
TEL
0153-82-2015(事務室)
0153-82-2364(職員室)
FAX
0153-82-2021
年間行事予定表